お疲れ様です。ご覧いただきありがとうございます。
本日は、暗号資産について記事を一本書かせていただこうと思います。
近年、最高値を更新し続けている暗号資産。
「なんだか難しそう」「値動きが激しくて危ないのでは?」という印象を持たれがちですが、今の法定通貨や暗号資産の概要を落ち着いて理解すれば、身近なお金やインターネットの延長線上にある存在であることが分かります。
暗号資産は怪しいものでもなんでもなく、お金のような使い方ができる”新しい技術”です。
本記事では、そんな暗号資産の歴史・代表的な銘柄・法定通貨との違いや、なぜ普及しているのかまでをお話ししていきます。
目次
暗号資産はブロックチェーン技術に支えられる「デジタルな財産価値」

暗号資産の簡単な概要
暗号資産とは、インターネット上だけでやり取りできるデジタルな“財産的価値”のことです。
暗号資産の取引は“ブロックチェーン”と呼ばれる台帳に全て記録されています。これを世界中の暗号資産業界参加者が相互に監視することで記録の改ざんを防ぐ仕組みになっています。
暗号資産を支えるブロックチェーンとは
ブロックチェーンをたとえ話で説明すると、「皆で監視する取引記録ノート」です。暗号資産の取引(送金など)を行ったら、その出来事をノートに書き込んでいくイメージです。
書き込まれたページは『ブロック』としてホチキス留めし、次のページへ進みます。ページを閉じる前に、見回り係(マイナー/バリデータ)が取引の正当性をチェック(計算)して、問題がなければホチキス留めをして改ざんできないようにします。
そして、このノートは写しを世界中の暗号資産参加者が持っています。
もし、過去のページをこっそり書き換え(記録の改ざん)たとしても、ほかの写しと合わなくなるのですぐバレます。送金の「サイン」は本人だけが押せる電子印(秘密鍵/署名)を使用するため、記録との齟齬があると取引は成立しません。
こうして中央の会計係がいなくても、みんなで記録の正しさを保てる仕組みがブロックチェーンです。
チェックリスト
- “取引のデータ”を世界中の皆で管理する仕組み(銀行のような中央管理者がいない)
- 世界共通のルールで24時間365日動くグローバルなネットワーク
- 取引履歴は改ざんできない
どのようにして暗号資産は生まれたのか?
簡単に、暗号資産が生まれたきっかけをお話しいたします。
暗号資産は2008年に「サトシ・ナカモト」という人物(あるいは集団)がビットコインの論文(ホワイトペーパー)を公開したことが起源です。
論文の内容をコンパクトにまとめると、“銀行のような中央の第三者を介さずに、二重支出を防ぐ仕組みを”という内容を示したものです。
そして論文が公開されて約1年後の2009年、世界で初めての分散型暗号資産「ビットコイン(BTC)」のネットワークが稼働開始しました。
| 年 | 出来事 | 意味 |
|---|---|---|
| 2010 | ビットコインでピザを購入(5/22に1万BTCで2枚) | 初めて「モノと交換」できた |
| 2013 | 価格が急上昇→急落 | 注目が集まり値動きが激化 |
| 2014 | Mt.Gox(当時の大手取引所)が破綻 | 暗号資産の不安視が広がる |
| 2017 | SegWit=取引データを軽くする改良/BCH分岐(8/1)=考え方の違いで別チェーン誕生 | 使いやすさの改善と方針の分岐 |
| 2018 | Lightning Network=少額を素早く・安く送る「裏道」本格運用 | 小口送金が便利に |
| 2020 | 第3回半減期=新規発行ペースが半分に | 供給ペースが落ちる |
| 2021 | エルサルバドルが法定通貨に採用(9月) | 初の法定通貨採用 |
| 2023 | Ordinals・BRC-20=ビットコイン上のNFT/トークンが話題 | 利用が広がり手数料も活発化 |
| 2024 | 第4回半減期(4月)/米国で現物BTC ETFが上場(1月) | 投資しやすさが向上 |
代表的な暗号資産5つ

BTC-暗号資産の王様-
ビットコインは最初に誕生した暗号資産で、最大級の時価総額を誇ります。
特徴は「発行上限が2,100万枚」と決められていることと、マイニング(計算作業)によるセキュリティ確保です。おおよそ4年ごとに新規発行のペースが半分になる「半減期」があり、インフレしにくい設計になっています。近年は「デジタルゴールド」のように長期保有の対象とみなす投資家や企業も増え、ETFなどの金融商品を通じて間接的に保有する選択肢の登場などで注目を集めています。
ETH-多彩なアプリケーションの土台-
イーサリアムは「プログラムが動くブロックチェーン」です。ここで動くプログラムは「スマートコントラクト」と呼ばれるもので、貸付・為替・保険などの金融サービスやゲーム内アイテムの所有権、会員証・チケットの配布など多彩なアプリ(dApps)の土台になる機能です。
2022年に省エネ型のコンセンサス(PoS)へ移行し、2024年には「Dencun」アップグレードでロールアップの手数料を大幅に抑えるなど、拡張機能により強化されているのが魅力です。ネットワーク手数料の支払いと、ネットワークを守るためのステーキングと呼ばれるものにも使用されています。
XRP-高速送金と小手数料を実現-
XRPは、アメリカのリップル社が発行している「XRPレジャー」というネットワークで動く通貨です。
XRPは海外送金を速く・安く行える特徴があります。銀行システムでは送金に数日、また手数料が数千円ほどかかりますが、XRPは数秒で送金が完了し、手数料も数円程度に抑えられます。
XRPは最初に1000億枚まとめて作られ、マイニングで増えることはありません。リップル社は保有分をエスクロー(時間ロック)で管理し、毎月少しずつ市場に出す運用をしています。国をまたぐ送金の“つなぎ役”として使いやすいとされます。
SOL-ゲームなどで活躍期待-
ソラナは「高速処理と低手数料」を強みとするブロックチェーンです。
時系列(時間)の証明を活用したProof of History(PoH)という仕組みを取り入れ、並列処理と合わせて高い処理能力を発揮することが出来る設計です。手数料が安く、リアルタイム性が求められるアプリや、NFT・ミームトークンなどの個人発行トークンが活発にやり取りされています。
ETHで言う「スマートコントラクト」に近いシステムも導入されています。これをソラナでは「プログラム」と呼びます。
ミームコイン-冗談交じりの暗号資産-
ミームコインは、インターネットのミーム(ネタ・ジョーク)やキャラクターを題材にしたトークンの総称です。
代表例は、ジョークから始まってコミュニティに支えられてきた「ドージコイン(DOGE)」、イーサリアム上で誕生した「柴犬(SHIB)」、2023年に急拡大した「PEPE」などが挙げられます。基本的には実用性よりもコミュニティ主導の熱量や話題性で価格が大きく動きやすく、短期的な値動きが非常に高いのが特徴です。投資家にはその値動きの激しさから「宝くじ的」に語られることもあります。
暗号資産と法定通貨の違い

法定通貨
ドルや円といった法定通貨は、各国の中央銀行や行政がその価値を保証しています。つまり”強制通用力(日本なら日本銀行券は支払い手段として法的に認められる)”を持つお金ということです。法定通貨の供給量や金利は金融政策で調整することが出来ます。
銀行口座や決済インフラ、預金保険など制度面もしっかり整備されています。価格の安定性や法的地位は、暗号資産に比べて高いです。
暗号資産
暗号資産には国家のような発行主体がありません。暗号技術と合意形成で、ユーザー間の価値移転を実現しています。世界中どこでもいつでも、インターネットとスマホがあれば銀行のような第三者を介さずに取引ができます。
暗号資産には、国際送金の手軽さや手数料の圧縮、暗号資産に関連するプログラムで新しいサービスを作れるといった、法定通貨にはない柔軟性があります。
一方で価格変動が大きい、送金ミス等のリカバリー手段がない、国や地域ごとに制度や規制が異なる等、ルールが明確になっていないという特徴もあります。
なぜ暗号資産が普及しているのか?
投資・分散目的
ビットコインは2100万枚の供給上限が決まっています。これは法定通貨と異なる値動きをする可能性があるため、ポートフォリオの一部として保有する投資家がいます。
法定通貨は国の決定で供給量を操作することが出来ます。極端に言えば、刷ろうと思えば無限にすることが出来ます。このようなインフレリスクが、ビットコインのような暗号資産にありません。そのため、リスクヘッジとしてポートフォリオに組み込む人も多いです。
また、米国で現物ビットコインETFが承認され、証券口座から手軽にアクセスしやすくなったことも普及の理由です。
国際送金・決済の新しい選択肢になる
暗号資産には、XRPやソラナ、イーサリアムのレイヤー2コインなど、少額・高速・24時間の送金を実現するものがあります。
従来の国際送金に比べて、時間帯や休日の制約を受けにくい点は非常に魅力的です(ただし、実際のコストや時間は、利用するサービス・通貨・ネットワーク混雑度で変わります)
とあるクリエイターが報酬を暗号資産で受け取ったという事例もあります。国をまたいでも高速で、手数料を抑えて送金できる点に注目している人が、送金特化型の暗号資産を使用しています。
“プログラムで動くお金”が新しいアプリを生む
イーサリアムを中心に、スマートコントラクトで貸借・取引・保険・ポイント・チケット関連の多様なアプリ(dApps)というものが誕生しています。
(dApps=分散型アプリ)とは、特定の会社のサーバーではなくブロックチェーン上で動くアプリのことです。アプリ内のルールはスマートコントラクトに記録されており、だれでも同じ条件で使うことが出来ます。また、止まりにくく、改ざんされにくいのが特徴です。
NFTでデジタル資産(写真、イラストなど)の所有権を表現したり、DAOでインターネット上の合意形成を行ったりと、従来のウェブにはなかった仕組みが拡がっています。
企業の財務戦略・決済手段の多様化
一部の企業は、財務の分散や価値保存の期待からビットコインをバランスシートに組み入れたり、顧客の決済の選択肢として暗号資産対応を進めたりしています。
たとえば米マイクロストラテジー(MicroStrategy)は、2020年以降「会社の貯金箱」として長期でビットコインを保有する方針を掲げ、株式や社債などで資金調達しながら保有を拡大しています。日本でもメタプラネットが2024年から準備資産としてのビットコインを購入するなど、バランスシートに組み入れる動きが広がっています。
これはETFやカストディ(保管)サービスの普及で、法人が扱いやすい環境が整いつつある証拠でしょう。
まとめ:暗号資産は新しい価値であり、資産である

いかがだったでしょうか?暗号資産の世界を少しでも知っていただけたら幸いです。
暗号資産は、「中央がすべてを管理する」世界とは異なる発想で設計された、お金に変わる新しい”価値”であり”資産”です。ビットコイン誕生により生まれた”分散型の通貨設計”は、その後のイーサリアムやソラナ、XRPなど多様なコインを生み、ミームコインのようなカルチャー的な広がりも見せています。
一方で、ボラティリティや自己管理、規制・税務への理解など、従来の金融以上に“学びながら使う姿勢”は法定通貨同様に求められるものです。
本記事が、暗号資産を“怖いもの”ではなく“分かれば選べるもの”として捉え直すきっかけになれば幸いです。
※本記事は特定の投資を推奨するものではありません。利用にあたっては最新の法令・税制・各サービスの規約をご確認ください。
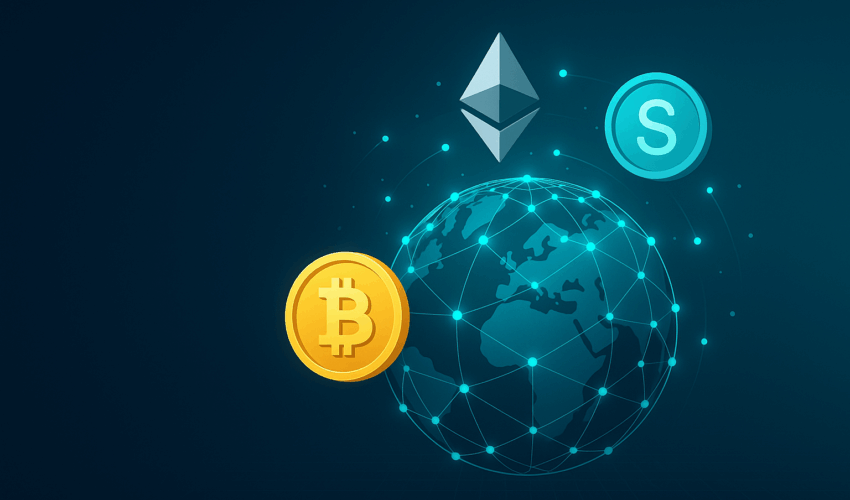

この記事へのコメントはありません。